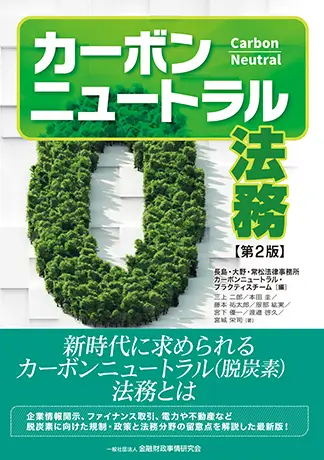
書籍
『カーボンニュートラル法務 第2版』
金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)
- インフラ/エネルギー/環境
- 発電プロジェクト/再生可能エネルギー
- 環境法
- ファイナンス
Publication

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
2023年10月7日、米国カリフォルニア州知事が、「気候データ説明責任パッケージ」(Climate Accountability Package)と呼ばれる一連の気候変動関連データの報告や開示を義務付ける法案に署名しました。この気候データ説明責任パッケージは、「企業気候データ説明責任法」(SB253:Climate Corporate Data Accountability Act)(以下「SB253」といいます。)※1と「温室効果ガス:気候関連財務リスク」(SB261:Greenhouse gases: climate-related financial risk)(以下「SB261」といいます。)※2の2つの法案で構成されます。以下に詳しく述べるとおり、これらの新たな法律の効力発生後は、カリフォルニア州で事業を行い、法律で定められた閾値を超える年間総売上高のある企業は、いわゆるスコープ3を含む温室効果ガス排出量及び気候関連財務リスクを報告及び開示することが義務付けられることになります。このような内容の法案の成立は連邦と州を含めて全米初であり、また米国証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)が2022年に公表した気候情報開示規則改正案と比較しても一歩踏み込んだ内容となっていることから、今回の新法はカリフォルニア州で事業を行う企業のみならず、米国内外におけるビジネスや法規制のあり方にも大きな影響を及ぼすと考えられます。そこで本ニュースレターでは、これらの新法の概要を解説した上で、SECの規則改正案や日本における類似制度とも比較し、企業に与える影響を分析いたします。
SB253は、報告企業(reporting entity)に対して、カリフォルニア州が指定する排出量報告機関(emissions reporting organization)に温室効果ガス排出量を報告することを義務付けています。報告された情報は、排出量報告機関が創設するデジタルプラットフォーム上で公開されます。そして、「報告企業」とは、米国のいずれかの州法、コロンビア特別区の法律又は米国議会の法律に基づき設立されたパートナーシップ(partnership)、会社(corporation)、有限責任会社(limited liability company)又はその他の事業体であって、前事業年度の年間総売上高が10億ドルを超え、カリフォルニア州において事業を行う者(does business in California)と定義されています。この定義によれば、報告企業は米国法に基づいて設立された事業体が対象となりますので、日本企業に関してはその米国子会社等が年間総売上高の閾値を超えるかどうか、カリフォルニア州において事業を行っているかどうかを判断することになります。もっとも、後述するように、報告企業はいわゆるスコープ3の温室効果ガス排出量の報告も義務付けられるため、日本企業の米国子会社等が報告企業の定義に該当しないとしても、日本企業やその米国子会社等がある報告企業のサプライチェーンを構成する場合には、開示義務を負う企業のスコープ3の排出量算定に際して、当該企業から一定の協力を求められることが想定されるという点には注意が必要です。また、要件該当性の判断に際して、「カリフォルニア州において事業を行う」という要件はSB253上定義されておらず、例えばカリフォルニア州において拠点が置かれている必要があるのかといった点が不明確になっています。この点は、以下で述べるように、今後カリフォルニア州大気資源局(California Air Resourced Board)(以下「CARB」といいます。)が策定する規則において明確化されることが期待されます。
報告企業は、以下のスコープに含まれる、当該報告企業の前年の温室効果ガス排出量を報告する義務があります。
上記のとおり、スコープ3は自社と取引のあるサプライチェーンからの排出量を指しますが、サプライチェーンからの排出量は、事業部門からの排出量の平均11.4倍で、その企業の温室効果ガス総排出量の約90%を占めるとも言われています※3。ソフトローの分野では、2023年6月にIFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会から公表されたIFRSサステナビリティ開示基準の気候関連開示(S2基準)において、温室効果ガス排出量に関し、スコープ1及びスコープ2だけでなく、スコープ3の開示も求められるようになりました(但し、当初の適用年度については、スコープ3開示を不要とする経過措置があります。)。各国の開示基準の策定に際し、事実上強い影響力のあるIFRSの基準においてもスコープ3の開示が必要となりますので、将来的には、スコープ3の排出量が法定開示化される流れになる可能性が高いと想定されるものの、とりわけこのスコープ3の排出量を報告企業全社に対して義務付けているのは、SB253の画期的な側面の1つといえます。
また、報告企業が開示する温室効果ガス排出量データについては、独立した第三者保証機関による保証を取得することが義務付けられています。すなわち、①スコープ1及びスコープ2については、2026年から2029年までの開示につき「限定的な保証」(limited assurance)を、2030年以降の開示につき「合理的な保証」(reasonable assurance)を取得する必要があります。また②スコープ3については、CARBが2026年に行うスコープ3に関する第三者保証要件のトレンドに係る分析に基づき、2027年1月1日までにスコープ3に関する第三者保証要件を制定できるものとされています。その場合、報告企業は、2030年以降の開示につき「限定的な保証」(limited assurance)を取得する必要があります。
温室効果ガス排出量の初回報告の時期は、①スコープ1及びスコープ2と②スコープ3で異なります。すなわち、①スコープ1及びスコープ2については、2026年以降毎年、CARBが定める日までにその前事業年度の温室効果ガス排出量を開示する必要があります。②スコープ3については、2027年以降毎年、スコープ1及びスコープ2の開示を行ってから180日以内に、その前事業年度の温室効果ガス排出量を開示する必要があります。
SB253によれば、今後CARBの定める規則において、温室効果ガス排出量の非開示、開示遅延、不十分な開示に関して、50万ドルを超えない範囲の行政罰を定めることとされています。また、CARBは、この行政罰を課すに当たっては、報告企業の過去及び現在の遵守状況、SB253に基づく開示の遵守のための公正な措置を定めていたかどうかなどを含むあらゆる事情を考慮するものとされています。さらに、スコープ3については情報の正確性の担保が難しいことから、合理的な根拠に基づき算出され、誠実に開示されたデータに関しては行政罰の対象とならず、また2027年から2030年の間は非開示のみが行政罰の対象とされており、一定の配慮がなされています。
SB253はCARBに対して、2025年1月1日までに、以下の内容を含むSB253に関する詳細な規則を定めることを義務付けています。
上記のように、今後策定されるCARBの規則によって、SB253に基づく温室効果ガス排出量の報告義務の内容、報告期限、保証機関による保証、不遵守の場合の制裁などが明確化されることが期待されます。また、上記1.で述べたとおり、報告企業に該当するための要件である「カリフォルニア州において事業を行う」の定義など、SB253で不明確になっている点が規則で明確化されるかどうかも注目する必要があります。
SB261は、対象企業(covered entity)に対して、(1)①気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)(以下「TFCD」といいます。)が2017年6月に公表した、気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言最終報告書(Final Report of Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)(2017年6月)又はTFCDの承継機関が公表する類似のフレームワークに基づいた気候関連財務リスク(climate-related financial risk)、及び②当該気候関連財務リスクの軽減策と対応策を記載した気候関連財務リスク報告書を作成、提出すること、並びに(2)自身のウェブサイトで当該報告書を公開することを義務付けています。そして、「対象企業」とは、米国のいずれかの州法、コロンビア特別区の法律又は米国議会の法律に基づき設立されたパートナーシップ(partnership)、会社(corporation)、有限責任会社(limited liability company)又はその他の事業体であって、前事業年度の年間総売上高が5億ドルを超え、カリフォルニア州において事業を行う者(does business in California)と定義されています。SB253と同様に、この定義によれば、報告企業は米国法に基づいて設立された事業体が対象となりますので、日本企業に関してはその米国子会社等が年間総売上高の閾値を超えるかどうか、カリフォルニア州において事業を行っているかどうかを判断することになります。また、「カリフォルニア州において事業を行う」という要件がSB261上定義されていないという点もSB253と同様であり、CARBが今後策定する規則による明確化が期待されます。なお、対象企業には、カリフォルニア州保険局(Department of Insurance)によって規制対象となっている事業体及び他の州において保険業を営む事業体は含まないものとされています。
SB261において対象企業が開示を義務付けられる「気候関連財務リスク」は、気候に関連する物理的及び移行リスク※4によって生じ得る、即時的及び長期的な財務に対する重大な損害リスクをいうと定義されています。また、SB261に基づく報告書では温室効果ガス排出量の開示は求められていませんが、対象企業が当該報告書において温室効果ガス排出量やその自主的な軽減について記載することを選択した場合、当該データは第三者機関による認証を取得する必要があるものとされています。なお、グループ内で複数の対象企業が存在する場合は、親会社においてグループ会社全体のリスクを統合した上で報告書を作成、公表することができ、その場合グループ内の子会社が対象企業に該当する場合であっても、報告書を作成、公表する必要はないものとされています。
また、CARBは、その選定する気候報告機関(climate reporting organization)と契約し、公開された気候関連財務リスク報告書の内容を産業別に分析し、隔年でその分析結果に関する報告書を公表することになっています。その報告書において対象企業名まで公表されるかどうかはSB261上では明らかではありませんが、不十分な報告書も特定することとされています。
対象企業は、2026年1月1日までに初回の気候関連財務リスク報告書の作成、提出及び公表を行い、その後は隔年で(すなわち、2年ごとに)行う必要があります。
SB261によれば、今後CARBの定める規則において、報告書の非公開及び不十分な内容の報告書の提出に関して、5万ドルを超えない範囲の行政罰を定めることとされています。また、CARBは、この行政罰を課すに当たっては、対象企業の過去及び現在の遵守状況、SB261に基づく開示の遵守のための公正な措置を定めていたかどうかなどを含むあらゆる事情を考慮するものとされています。
また、対象企業が完全な報告書を提出できない場合は、可能な限りの開示を行い、開示不足の点についての詳細な説明と完全な開示を行うために対象企業が講じる措置を記載しなければならないものとされています。もっとも、このような措置を講じた場合に、上記の行政罰の対象外となるかどうか(いわゆるセーフハーバーとなるかどうか)については、SB261上は明らかにされておらず、CARBが策定する規則での明確化が期待されます。
SB261はCARBに対して、CARBによるSB261の管理及び執行に要する費用を補うためのフィーの設定や行政罰の設定などを内容とする、SB261に関する詳細な規則を定めることを義務付けています。SB253とは異なり、規則の制定期限が明記されていない点が特徴的ですが、2025年1月1日までとなっているSB253に関する規則と同時に公表されるか、遅くとも初回報告書の提出期限である2026年1月1日に間に合うように公表されることが想定されますので、今後の動向を注視する必要があります。
2022年3月21日、SECは登録届出書及びその後の定期報告書において、上場企業に対して一定の気候関連の情報を開示するよう義務付ける規則改正案を公表しました※5。この気候関連の情報には、当該企業の事業運営や財務状況に重要な影響を与える合理的な可能性のある気候関連リスクや、温室効果ガス排出量が含まれています。この温室効果ガス排出量に関しては、スコープ1及びスコープ2の排出量は全上場企業に対して開示の義務を課している一方で、スコープ3については、上場企業がスコープ3の排出量が重要(material)であると考えているか、スコープ3の排出量を含む温室効果ガス排出量に関する指標や目標を設定している場合にのみ開示を義務付けています。
したがって、SB253が対象となる全ての報告企業に対してスコープ3の排出量の報告及び開示を義務付けている点と大きな相違があるといえます。そして、上述のとおり、スコープ3の排出量全体に占める割合が約90%であることを踏まえると、スコープ3の排出量の開示を義務付けることは極めて大きな意義があります。また、SECの規則改正案が上場企業に対してのみ適用されるのに対して、気候データ説明責任パッケージは、上場企業か非上場企業であるかを問わず、カリフォルニア州で事業を行い、一定の総売上高の閾値を超える全ての企業に対して開示を義務付けている点でも違いがあるといえます。
このSECの規則改正案はまだ最終化されていませんので、最終化された規則がどのような形になるのか今後の動向に注目を要します。
2023年1月31日、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正され、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等において、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設されました※6。このうち、「ガバナンス」及び「リスク管理」については必須記載事項ですが、「戦略」及び「指標及び目標」については重要性に応じて記載が求められることになっています。この改正により、これらの項目に基づく開示が必要となったものの、その具体的な記載方法については詳細に規定されておらず、各企業の現在の取組状況に応じて柔軟に記載できる枠組みとなっています。
温室効果ガス排出量の開示については、別途「記述情報の開示に関する原則(別添)-サステナビリティ情報の開示について-」が公表され、各企業の業態や経営環境等を踏まえた重要性の判断を前提としつつ、スコープ1及びスコープ2の排出量の積極的な開示が期待されるという推奨にとどまりました※7。また、金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントにおいて、投資家との建設的な対話に資する情報を積極的に提供していく観点や、2022年3月にISSBから公表されたサステナビリティ開示基準の公開草案ではサステナビリティ情報について財務情報との結合性や財務諸表と同じ報告期間を対象とすることが求められていることを踏まえ、スコープ1及びスコープ2の開示については、望ましい開示実務の確立に向け、今後各企業の状況を踏まえながら検討いただくことが望まれる、との考え方を示していました(2023年1月31日「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等)」No.148)※8。このように、現状の日本の有価証券報告書等における温室効果ガス排出量の開示は、スコープ1及びスコープ2の排出量の開示を義務付けるSECの規則案と比較しても一歩後退した開示規制となっています。
もっとも、上述のとおり、IFRSサステナビリティ開示基準の気候関連開示(S2基準)では、温室効果ガス排出量に関し、スコープ3の開示も求められるようになりましたので、今後、日本においても、温室効果ガス排出量の法定開示化に向けた議論が進んでいくものと想定されます※9。
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」といいます。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスを排出する一定の者(「特定排出者」と定義され、全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算で1,500kl/年以上となる事業者や省エネ法上の特定貨物輸送事業者・特定荷主等を指します。)に対して、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することを義務付けています(温対法26条1項)。これにより、特定排出者は、自らの排出量を算定し、毎年7月末日(輸送事業者は6月末日)までに、直近の算定排出量算定期間に係る排出量情報を事業所管大臣へ報告する必要があります(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令4条参照)。そして、事業所管大臣は報告された情報を集計して環境大臣及び経済産業大臣へ通知し(温対法28条)、環境大臣及び経済産業大臣はこれを集計して公表することが求められています(同法29条)。もっとも、この温対法に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度は、自らの事業活動に伴う直接排出とエネルギー使用に伴う間接排出による温室効果ガスの排出量を算定範囲としているため、基本的にスコープ3の排出量は含まれないことになります。
また、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「省エネ法」といいます。)は、大要、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を「特定事業者等」として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めていますが、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資への注目が高まり、企業のサステナビリティ情報の開示に対する要請も高まりつつあること等を踏まえ、特定事業者等からの開示宣言に基づく省エネ法定期報告書等の情報を開示する枠組み(任意開示制度)の導入が予定されています。令和5年度は東証プライム上場企業を対象とする試行運用とし、令和6年度から全ての特定事業者等を対象とする本格運用に移行する予定です。この任意開示制度においては、温対法関連情報として、温室効果ガス排出量等を開示対象とすることが可能とされています。但し、あくまで任意開示制度ですので、開示を強制されるものではありません。
したがって、スコープ3までの開示を義務付けるSB253は、これらの制度と比較しても報告企業に対してより充実した情報開示を求めるものといえます。
気候データ説明責任パッケージは、スコープ3の排出量の開示も全報告企業に義務付ける点において、極めて重要な意義を有する法律です。すなわち、カリフォルニア州で事業を行い、総売上高の閾値を超えるような大企業については、スコープ3の排出量の開示まで義務付けられることにより、本法に基づき開示義務を負う企業のサプライチェーンを構成する日本企業やその米国子会社等についても、開示義務を負う企業のスコープ3の排出量算定に際して、当該企業から一定の協力を求められることになるものと想定されます。したがって、直接的には開示義務の対象とならない企業であっても、既存の取引先の中に開示義務の対象となる企業が含まれるか否かの洗い出しが必要でしょうし、既存の取引先に開示義務を負う企業が含まれる場合はもちろんですが、カリフォルニア州という経済規模の大きい州に関連する取引を今後行う可能性がある場合には、自社の温室効果ガス排出量を積極的に把握する必要があると思われます。その意味で、本法はカリフォルニア州のみならず、世界的な気候関連情報の開示制度や米国内外の企業に大きな影響力を持つ、重要な法律といえます。
また、今後CARBが策定する規則において、「カリフォルニア州で事業を行う」の定義など法律ではまだ不明確な部分が明確化されることが期待されますので、今後の動向に注視する必要があります。
※4
例示として、企業運営、商品とサービスの提供、サプライチェーン、従業員の健康と安全、投資、融資先と借り手の財務状況、株主価値、消費者需要、金融市場と経済の健全性に対するリスクが挙げられています。
※9
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)によるIFRSサステナビリティ開示基準に関しては、宮下優一「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)によるIFRSサステナビリティ開示基準の最終化(速報)」(NO&T Capital Market Legal Update ~キャピタルマーケットニュースレター~ No.27(2023年7月))(https://www.nagashima.com/publications/publication20230705-1/)も参照。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
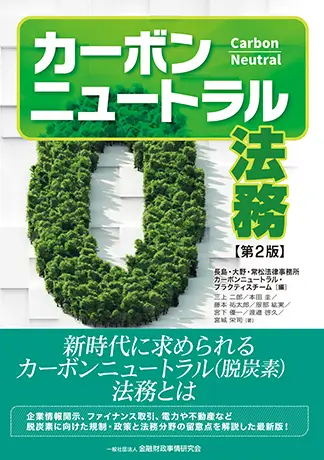
書籍
金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)
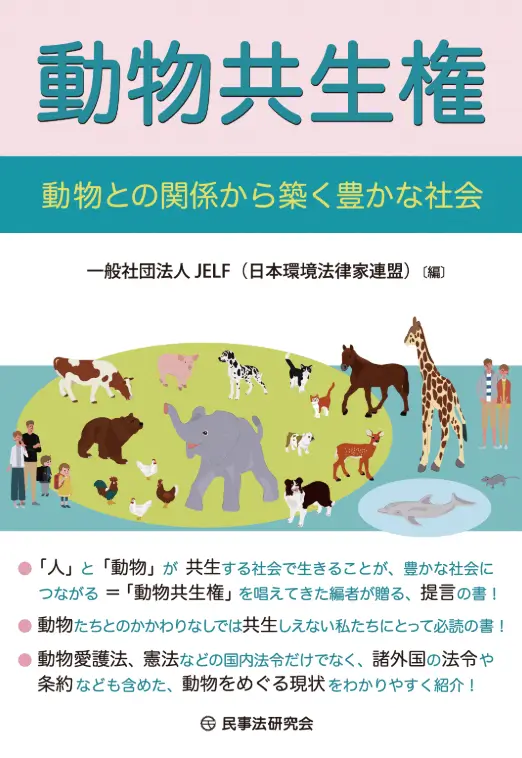
書籍
民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)
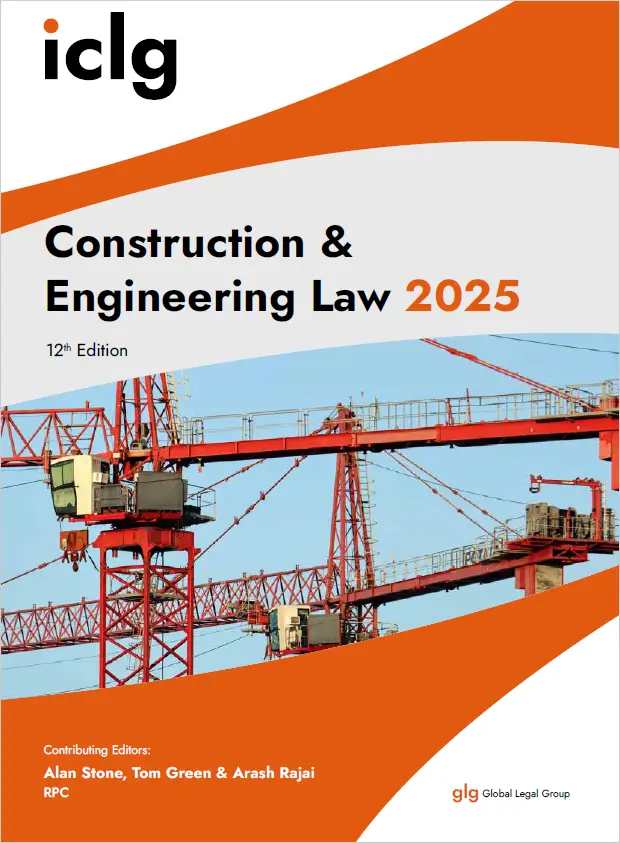
論文/記事
(2025年8月)
杉本花織

論文/記事
(2025年8月)
井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)
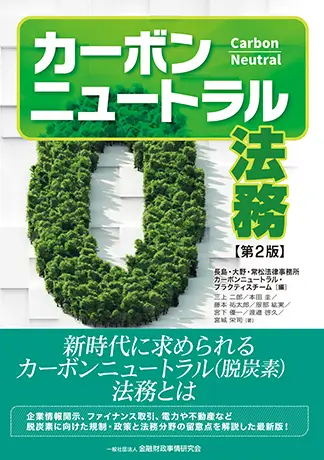
書籍
金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)
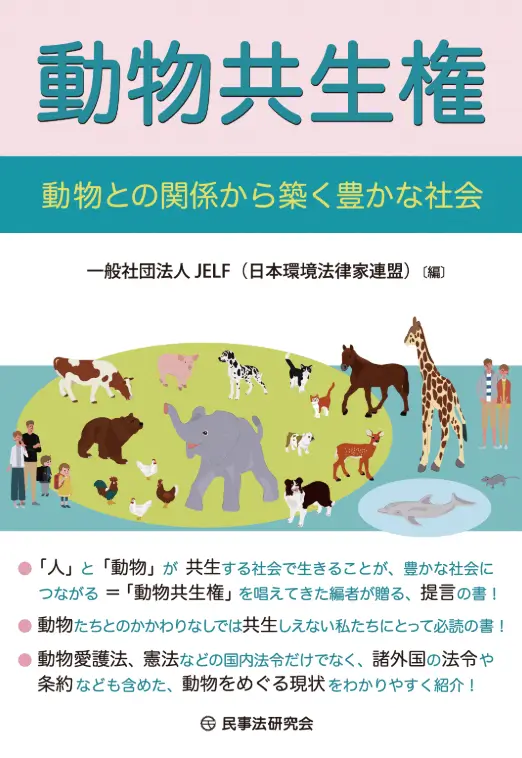
書籍
民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)

ニュースレター
宮下優一、薄実穂(共著)
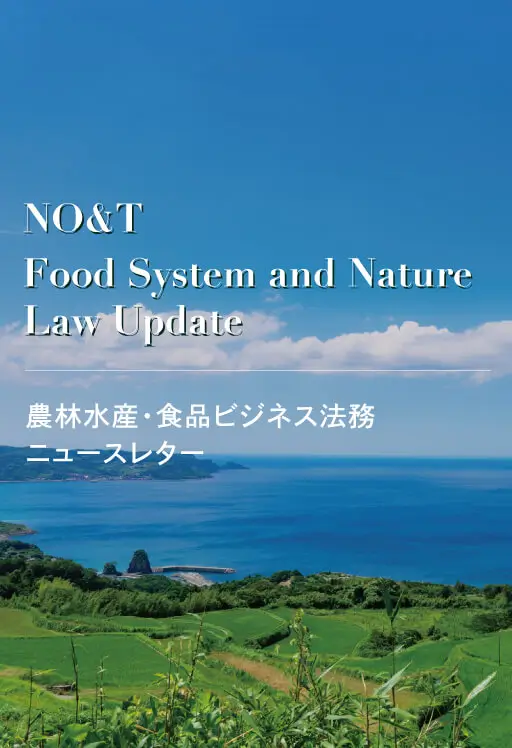
ニュースレター
宮城栄司、井柳春菜(共著)

ニュースレター
塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター
山本匡

ニュースレター
梶原啓

ニュースレター
塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

ニュースレター
塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター
塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

ニュースレター
塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター
塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター
塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター
塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

ニュースレター
塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

ニュースレター
塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)