
論文/記事
最新判例アンテナ 第91回 クラウドサービスで取り扱う従業員個人データを雇用主であるユーザー企業へ提供することに関して,第三者提供についての本人の黙示的な同意を認め,個人情報保護法27条1項違反を否定した事例 (東京地決令7.3.27公正取引委員会審決等データベース)
(2025年12月)
三笘裕、高村真悠子(共著)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 個人情報保護・プライバシー
- 独占禁止法/競争法
- その他独占禁止法違反事件対応
Publication
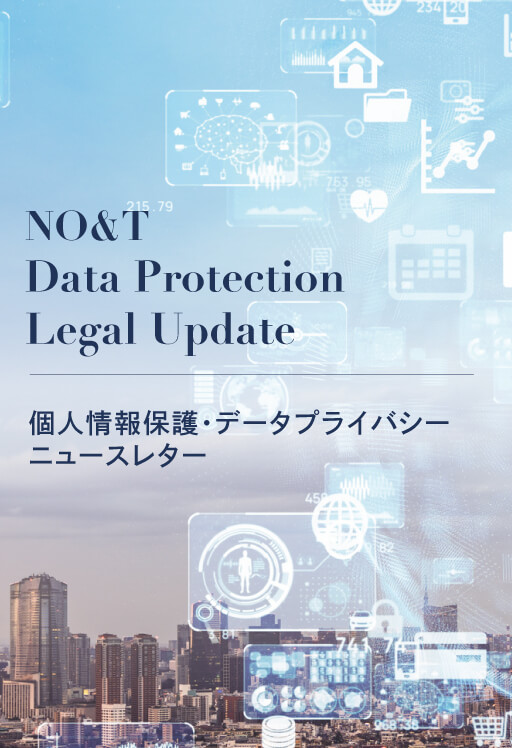
ニュースレター
<XR/メタバース Update> 「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会 報告書2024」の公表(2024年12月)
個人情報保護・プライバシー 2024年の振り返りと2025年の展望 ~日本編~(2025年1月)
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。
個人情報保護委員会(以下「委員会」という)は、2023年11月頃より、個人情報保護法(以下「法」という)の「いわゆる3年ごと見直し」※1の検討を開始し、関係団体や有識者からのヒアリングを実施して議論・検討を進めてきた結果を踏まえて、本年6月27日に、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」(以下「本中間整理」という)を公表した。本中間整理は、7月30日午前0時までのパブリック・コメントに付されている※2。
本中間整理は、これまでの議論・検討を踏まえた委員会の現時点での「考え方」が示されているものであり、今後、パブリック・コメントの意見も踏まえて最終的な方向性のとりまとめを行い、来年の通常国会において改正法案が提出されることが予定されている。生体データ、こどもの個人情報等の規律、漏えい等報告義務の軽減等、実務上、多くの事業者に影響がありうる事項が対象となっており、改正法の具体的内容によっては、プライバシーポリシー等の修正・変更、安全管理措置の変更、漏えい等発生時のマニュアルの変更等の対応が必要となる可能性があるため、事業者としても、自社への影響を含めて、現状の委員会の考え方を正確に把握しておく必要性は高いと思われる。
そこで本ニュースレターでは、関連する現行法の規律を説明した上で、本中間整理で示されている「考え方」の概要、及びそのポイントについて紹介する(なお、本ニュースレターで紹介している本中間整理の「考え方」については、執筆者が一部要約したものであり、より正確なニュアンスを理解するためには、本中間整理の原文をご参照いただきたい)。
本中間整理は、大きな枠組みとしては、「個人の権利利益のより実質的な保護の在り方」、「実効性のある監視・監督の在り方」、「データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方」、「その他」に分けられており、さらに細かく具体的な検討項目が記載されているが、以下では、それぞれの具体的な検討項目について説明していく。
| 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方 |
|---|
個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方
|
| 第三者提供規制の在り方(オプトアウト等) |
| こどもの個人情報等に関する規律の在り方 |
| 個人の権利救済手段の在り方 |
| 実効性のある監視・監督の在り方 |
| 課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方 |
| 刑事罰の在り方 |
| 漏えい等報告・本人通知の在り方 |
| データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方 |
| 本人同意を要しないデータ利活用等の在り方 |
| 民間における自主的な取組の促進 |
| その他 |
情報通信技術等の高度化に伴い、大量の個人情報を取り扱うビジネス・サービス等が生まれる一方で、プライバシーを含む個人の権利利益が侵害されるリスクが高まっていることや、破産者等情報のインターネット掲載事案や、犯罪者グループ等に名簿を提供する悪質な「名簿屋」事案等、個人情報が不適正に利用される事案も発生しており、本中間整理では、こうした状況に鑑み、技術的な動向等を十分に踏まえた、実質的な個人の権利利益の保護の在り方が検討されている。
【具体的な規律内容への言及】
個人情報の取扱いが問題となった事例の中には、個人情報に係る本人が不特定かつ多数と評価し得るものがあり※7、本中間整理では、適格消費者団体を前提とする団体訴訟制度(差止請求制度や被害回復制度)の創設は有効な権利救済手段の選択肢になり得るとされたものの、適格消費者団体の課題(専門性の確保、資金面での援助の必要性を含む。)があることに加え、関係団体から強く反対意見があったことを踏まえ、「その導入の必要性を含めて多角的な検討を行っていく必要」があるとの整理が示された※8。
適格消費者団体による団体訴訟制度が導入されれば、実務上、個人情報取扱事業者に与えるインパクトが大きいが、産業界からの強い反発があったことなどもあり、現時点において、団体訴訟制度の創設の見通しは不透明である。今後、ステークホルダーと議論するための場を設けること、2024年末までを目処に議論を深めていくこととされている。
破産者等情報のインターネット掲載事案、犯罪者グループ等に名簿を提供する悪質な「名簿屋」事案、転職先へのデータベースのID・パスワードの不正提供事案等、個人情報が不適正に利用される事案や、同一事業者が繰り返し漏えい等を起こしている事案が発生している。こうした悪質・重大な事案に対する厳罰化、迅速な執行等、実効性のある監視・監督の在り方が検討されている。
(参考:個人情報取扱事業者に対する現行法上の監視・監督の流れ)

(第277回個人情報保護委員会資料1の7頁から引用)
課徴金制度の導入については、過去の法改正の検討においても議論されており、令和2年改正法の法案審議においては、「違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、課徴金制度の導入については、我が国他法令における立法事例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討を行うこと」との附帯決議がなされていた。本中間整理においても、以下のとおり必要性も含めて継続的に検討することとされた。
課徴金については、関係団体からのヒアリングで強い反対意見が示されていることに加え、我が国の他法令における導入事例や国際的動向、個人の権利利益保護と事業者負担とのバランスを踏まえ、その導入の必要性を含めて検討する必要がある。
勧告・命令の在り方については、以下が示された。
個人情報取扱事業者等による法に違反する個人情報等の取扱いにより個人の権利利益の侵害が差し迫っている場合に直ちに中止命令を出すことの必要性や、法に違反する個人情報等の取扱いを行う個人情報取扱事業者等のみならず、これに関与する第三者に対しても行政上の措置をとることの必要性、法に違反する個人情報等の取扱いの中止のほかに個人の権利利益の保護に向けた措置を求めることの必要性の有無や手続保障など、その法制上の課題等について検討すべきである。
個人情報が不正に取り扱われた悪質な事例※11が増加傾向にあり、現行法の直罰規定がこうした事例を捕捉するのに十分でない可能性が指摘されていることを受けて、本中間整理では、以下の考えが示された。
個人情報が不正に取り扱われた悪質事案の類型が様々であることを踏まえ、法の直罰規定がこれらの事案を過不足なく対象としているかを検証し、その処罰範囲について検討するとともに、法定刑の適切性についても検討する必要がある。
さらに、個人情報の詐取等の不正取得が多数発生している状況を踏まえ、こうした行為を直罰規定の対象に含めるべきかについても検討する必要がある。
漏えい等報告に関しては、以下の考えが示された。
①上記のように、委員会がこれまでに受けた漏えい等報告を件数ベースでみると、漏えいした個人データに係る本人の数が1名である誤交付・誤送付案件が大半を占めているが、このようなケースは、当該本人にとっては深刻な事態になり得るものであり、本人通知の重要性は変わらないものの、本人通知が的確になされている限りにおいては、委員会に速報を提出する必要性が比較的小さい。また、②漏えい等又はそのおそれを認識した場合における適切な対処(漏えい等が生じたか否かの確認、本人通知、原因究明など)を行うための体制・手順が整備されていると考えられる事業者については、一定程度自主的な取組に委ねることも考えられる。そこで、例えば、体制・手順について認定個人情報保護団体などの第三者の確認を受けることを前提として、速報については、一定の範囲でこれを免除し、さらに①のようなケースについては確報について一定期間ごとの取りまとめ報告を許容することも考えられる。
違法な第三者提供に関しては、以下の考えが示された。
個人データが漏えい等した場合については事業者にこれらの義務が課されることとの均衡から、漏えい等との違いの有無も踏まえ、その必要性や報告等の対象となる範囲を検討する必要がある。
健康・医療、教育、防災、こども等の準公共分野を中心に、機微性の高い情報を含む個人情報等の利活用に係るニーズが強い。こうした中、政策の企画・立案段階から関係府省庁等とも連携した取組を進める等、個人の権利利益の保護を担保した上で、適正な個人情報等の利活用を促す方策が検討されている。
本人同意を要しないデータの利活用等の在り方に関しては、以下の考えが示された。
法で本人同意が求められる規定の在り方について、個人の権利利益の保護とデータ利活用とのバランスを考慮し、その整備を検討する必要がある。
まず、生成AIなどの、社会の基盤となり得る技術やサービスのように、社会にとって有益であり、公益性が高いと考えられる技術やサービスについて、既存の例外規定では対応が困難と考えられるものがある。これらの技術やサービスについては、社会的なニーズの高まりや、公益性の程度を踏まえて、例外規定を設けるための検討が必要である。この際、「いかなる技術・サービスに高い公益性が認められるか」について、極めて多様な価値判断を踏まえた上で高度な意思決定が必要になる。個人の権利利益の保護とデータ利活用の双方の観点から多様な価値判断が想定されるものであり、関係府省庁も含めた検討や意思決定が必要と考えられる。
また、医療機関等における研究活動等に係る利活用のニーズについても、公益性の程度や本人の権利利益保護とのバランスを踏まえて、例外規定に係る規律の在り方について検討する必要がある。(中略)こうした点等については、事業者の実情等も踏まえつつ、関係府省庁の関与を得ながら、ガイドラインの記載等についてステークホルダーと透明性のある形で議論する場の設定に向けて検討する必要がある。
民間における自主的な取組の促進に関しては、以下の考えが示された。
PIA・個人データの取扱いに関する責任者は、データガバナンス体制の構築において主要な要素となるものであり、その取組が促進されることが望ましい。他方、これらの義務化については、各主体における対応可能性や負担面などを踏まえ、慎重に検討を進める必要がある。
上記のほか、プロファイリング(本人に関する行動・関心等の情報を分析する処理)、個人情報等に関する概念の整理、プライバシー強化技術(「PETs」:Privacy Enhancing Technologies)の位置付けの整理、金融機関の海外送金時における送金者への情報提供義務の在り方、ゲノムデータに関する規律の在り方、委員会から行政機関等への各種事例等の情報提供の充実などの論点についても、ステークホルダーの意見やパブリック・コメント等の結果を踏まえ、引き続き検討することとされた。
また、委員会が関係の深いステークホルダーと透明性のある形で継続的に議論する場を設け、個人情報保護政策の方向性や、本人同意を要しない公益に資するデータ利活用に関係するガイドライン等の見直しの在り方などについて、検討を進めることも考えられている。
本ニュースレターでは、本中間整理で示されている「考え方」の概要及びそのポイントについて、関連する現行法の規律とともに紹介したが、特に、生体データについての規律やこどもの個人情報等の取扱いの規律、漏えい等報告義務の軽減等については、多くの事業者にとって実務的な影響が大きいと考えられる。また、課徴金や、適格消費者団体による団体訴訟制度(差止請求制度や被害回復制度)も、仮に導入された場合には個人だけでなく事業者にとってもインパクトが大きい。一方で、2024年5月21日に自由民主党政務調査会デジタル社会推進本部が公表した「デジタル・ニッポン2024」において、規制の見直し・運用に当たって政府は多くのステークホルダーの意見を聞き透明性を高めることが必要であることや、課徴金の導入や団体訴訟制度について慎重に議論すべきことが指摘されている。そして、このことに関して、本中間整理でも、パブリック・コメント終了後もステークホルダーと継続的な議論を行うプロセスを踏まえて各検討項目の方向性を見直すことも想定される旨を述べている。
このため、今後の個人情報保護法の見直しについての議論の状況は引き続き注視する必要があり、弊事務所でも、ニュースレター等を通じて最新の動向についてタイムリーにご紹介していく予定である。
※1
令和2年改正法の附則において、「政府は、この法律の施行後三年ごとに、(中略)、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定めており、当該附則を踏まえて、「いわゆる3年ごと見直し」として検討が開始された。
※3
目的外利用(法18条2項)、要配慮個人情報の取得(法20条2項)、個人データの第三者提供(法27条1項、28条1項)、個人関連情報の第三者提供(法31条1項)など。
※4
利用目的の通知(法21条1項)、個人情報の書面等による直接取得の場合の利用目的の明示(法21条2項)、漏えい等に関する本人への通知(法26条2項)など。
※5
具体的には、本人は、当該本人が識別される保有個人データについて、法の規定に違反する場合や、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等に、個人情報取扱事業者に対して、当該本人が識別される保有個人データの利用停止等又は第三者提供の停止を請求することができる(法35条)。
※6
委員会が実施したアンケート調査では、過去1年間で利用停止等・第三者提供の停止請求を受けた件数が10件を下回る企業が47%だったと報告されている。
※7
例えば、フェイスブック事件(2018年10月)、JapanTaxi事件(2018年11月、2019年9月)、内定辞退率提供事件(2019年)、新破産者マップ事件(2022年)、ビジネスプランニング事件(2024年1月)等。
※8
また、被害回復制度については、適格消費者団体の専門性の確保といった課題に加え、個人情報の漏えいに伴う損害賠償請求が極端な少額大量被害事案となること、立証上の問題があることが課題と考えられることから、更に慎重な検討が必要とされた。
※9
第286回個人情報保護委員会における3年ごと見直しの議論において、一部の委員から、「インターネット上の情報は様々なサイトを転々としながら表示され続けてしまう特性がある。それに加担してしまう第三者のプロバイダーやデジタルプラットフォーマーは、現行法では直接命令の対象者とはならないが、GDPRでは検索エンジン事業者やクラウドサービス事業者に対してデータ主体の削除要求に対応するよう求めた例もあるようである。(中略)このような例も参考としながら、プロバイダー等に対して故意犯の可能性があることを知りながら手を貸しているのと同様のことを行っているとして、データ主体の申立てに対応するよう何らかの求めを行う方法があるのかどうか検討していただきたい」という旨の発言があった。
※10
法179条。その他の直罰規定の例としては、法176条、180条、181条及び184条。
※11
大手学習塾の元講師が、児童の個人情報をSNSに投稿した事例等。
※12
参考:第284回個人情報保護委員会
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

論文/記事
(2025年12月)
三笘裕、高村真悠子(共著)

論文/記事
(2025年12月)
関口朋宏(共著)

論文/記事
(2025年12月)
安西統裕、早川健、一色健太(共著)
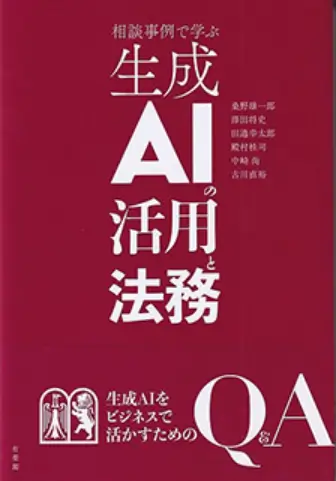
書籍
有斐閣 (2025年12月)
殿村桂司(共著)

論文/記事
(2025年12月)
鹿はせる、松﨑由晃(共著)

メディア
(2025年12月)
小川聖史(コメント)

ニュースレター
遠藤努

ニュースレター
大久保涼、髙橋優、渡辺雄太(共著)

論文/記事
(2025年12月)
鹿はせる、松﨑由晃(共著)

メディア
(2025年12月)
小川聖史(コメント)

論文/記事
(2025年11月)
関口朋宏(共著)

ニュースレター
殿村桂司、小松諒、渡辺雄太(共著)

ニュースレター
殿村桂司、小松諒、渡辺雄太(共著)
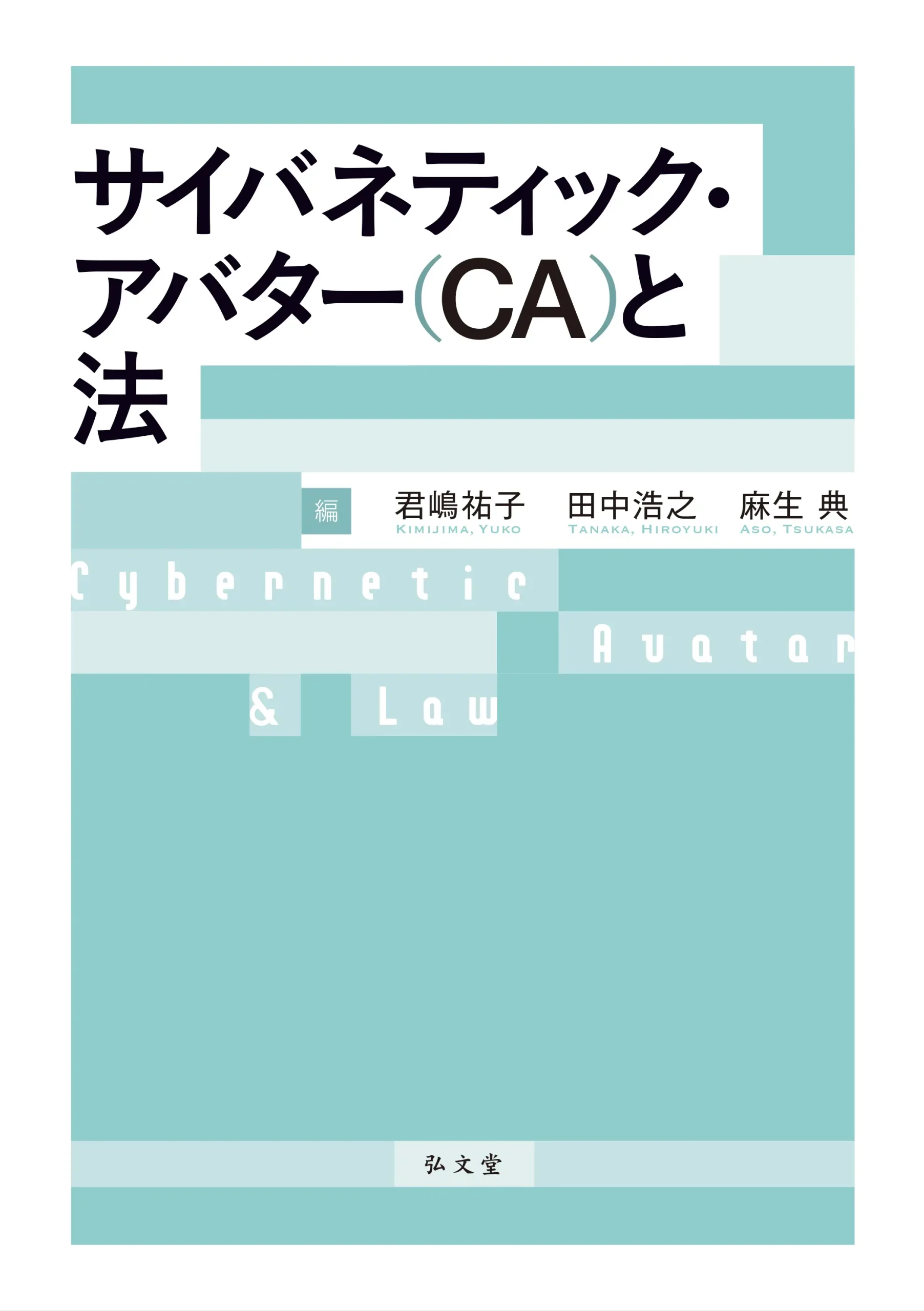
書籍
弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)

論文/記事
(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)

論文/記事
(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)
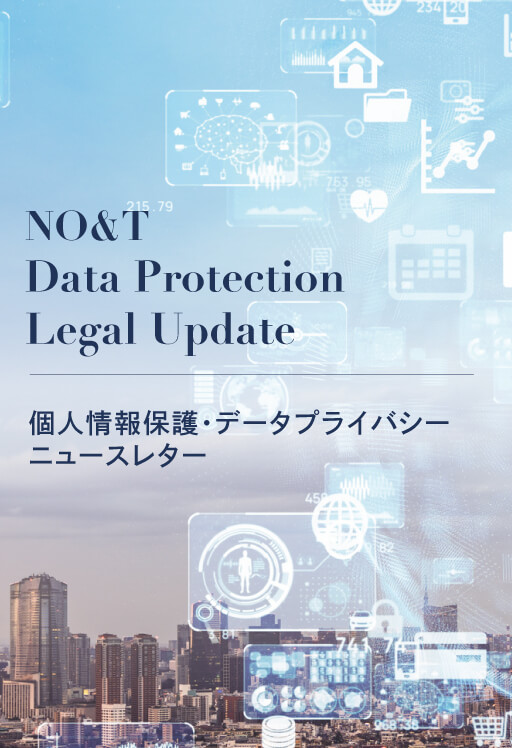
ニュースレター
森大樹、早川健(共著)

論文/記事
(2025年11月)
関口朋宏(共著)

論文/記事
(2025年10月)
関口朋宏(共著)

論文/記事
(2025年10月)
犬飼貴之